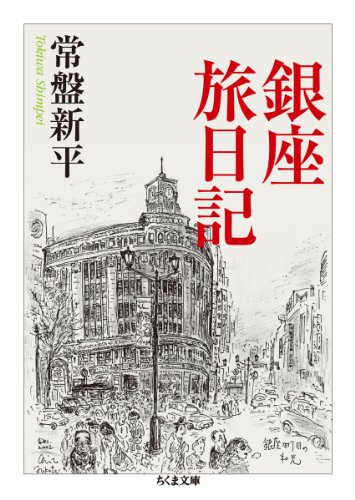『なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか パンと日本人の150年 』 阿古 真理
このタイトルだったら読まないけど、なんといっても阿古真理さんの著作だからね!阿古真理ファンの私としては著者名で読みました。で、期待通りの満足感!
パンが日本にやってきたのは、正確には種子島に漂着したポルトガルからの宣教師からなんだけど、でもほっとんどの人には無縁だったわけで、もっと一般にパンが浸透してきたのはいつかと言えば、やっぱり明治時代からだよね。
この時代に日本の職人が外国人の職人から技術を習得したりと四苦八苦してパン作りを習得してパン屋を開業しはじめ、外国人向けだけではなく日本人にウケるパンをと、アンパンという和風パンの金字塔が発明され、パンは洋行帰りの人を中心に都市の富裕層に受け入れられていきます。
当初、パンの先端都市は横浜だったのですが、関東大震災で多くの外国人とパン職人たちが神戸へ移動したことをきっかけに、日本のパンの勢力図は神戸を中心に関西圏へと移っていきます。実はこの勢力図は現在に至るまで影響があって、2016年時点でもパン消費量ランキングの上位は関西勢が独占しています。関西出身の阿古真理さんも、上京した当初、美味しいパン屋さん(ちゃんとしたバゲットやバタールなどのハードパンが置いてあるお店)がなかなか見つからずに困ったと書いていました。それから偶然にもこのブログの数エントリー前に出てくる、ベルギーの食生活が描かれた『フランダースのイモ』でも、関西人の山口潔子さんが、京都のパン屋さんのレベルの高さについて言及していました。
そう、やっぱりパン文化が進んでるかって、ハードパンがちゃんとしてるかですよね!めっちゃ皮の硬そうな香ばしそうなバゲットやバタールが並んでいるパン屋さんを見るとワクワクします。
ただ、日本はお米文化圏。日本でなかなかハードパンが受け入れられず、モチモチ食感の柔らかいパンが愛され続けているのも、水分をたっぷり含んだお米の食感に慣れているから。阿古真理さんは、そこに中華圏の粉物文化の影響も入り混じっているのではと、考察されています。
『生きて帰ってきた男――ある日本兵の戦争と戦後 』小熊英二
読んで良かった。
小熊さんのお父様である、謙二さんの戦前、戦中、戦後史。学者である小熊さんのお父さんなんだから、やっぱり学者だったりインテリな人なんだろうかとおもいきや、小さな商店を営む祖父母に育てられ、ご本人も零細企業を転々として最終的には小さな会社の経営者になったものの、基本的には学問や大学とは無縁の人だったそう。(小熊さんが学問の道に進んだのは、小学校教師の娘で教育熱心だったお母様の影響っぽい)
基本的に謙二さんのような一般的な庶民は、自らが体験した記録を残さない。だから戦争体験談といえば、高級将校や学生のようなインテリ層か、または自分の体験に強烈に思い入れのある人という偏ったものになりがちだった。
本書は、謙二さんの戦前、戦争中、戦後の記憶を、現代史家の林英一さんがインタビューし、それを小熊英二さんが当時の社会状況や政治的な背景を交えて文章化したものです。
軍部の愚かさは読んでいて怒りしか湧かないわ!謙二さんも言っていたけど、多くの人を死なせ、苦しめたこいつらがなんで反省もせずにいるのかと思う。ちゃんと責任とらせないから今みたいに「あの戦争は正しかった」みたいなことが性懲りもなく社会に出てくるんだな。
日本は戦争で被害を受けた国民への保障をしない方針(戦争の被害は国民が等しく受忍)で、保障らしきものはあくまで戦前からあった軍人恩給制度を適用させることだった。だから愚かなことをして責任取らなきゃいけない連中ほど階級が上だから恩給が手厚くて、バカな連中のせいで被害を受けた下の階級の人ほど手薄い。しかも当時、朝鮮や台湾にいて日本の戦争に巻き込まれた人はさらにその枠外という、ひっどいものだった。私はそれを恥ずかしながらこちらの本で初めて知りました。
こちらの本で画期的なのは、戦争体験、収容所体験で話が終わるのではなく、それらを体験した人の戦後から現在にかけての人生。戦争、収容所体験がその後の人生にどのような影響を及ぼすのかを追いかけているところだと思う。
決して愉快な話じゃないのに、私なんでこんなにスイスイと読めちゃったんだろう。なんかそういうスイスイ読み進めたくなる魅力があるんだろうな。
『銀座旅日記』常盤新平
なんてことない日記なんだけど、文庫本で持ち歩くのにいいし、なんとなくカバンに入れて読み終わっちゃった。
常盤新平さんってなんとなく若いイメージがあったけど、というか、単に常盤さんの若いころのエッセイを読んだだけだったと思うんだけど、こちらの本は晩年のおじいさんになってからの常盤さんの日記です。2003年から2006年まで。
なので、日記では日常的に病気ネタや老化ネタが登場します。あと「もう死にたい」的なこととか。
私はなんだかんだ言って、食べ物ネタに惹かれて読んでいった感じ。朝食メニューとか外食メニューが美味しそうで読んでいて楽しかった。出てくるお店をメモして探訪してみようかな、などと読みながら考えていたんだけど、終盤になると、けっこう「馴染みのお店が閉店した」みたいな話が出てくるので悲しい。
あと、登場するご家族の関係が複雑で、よく飲み込めなかった。前の奥様と現在の奥様は飲み込めたんだけど、お嬢さんが何人いらっしゃるのかとかがいまいちわからなかったんだけど、余計なお世話かw
『したくないことはしない』植草甚一の青春
植草甚一さんといえば、小柄で細身の体にサイケデリックなTシャツやベルボトムのパンツといったファンキーな服装に身を包み、街歩きと、古書あさりとジャズを愛する飄々としたご老人というイメージですが、「それ以前」の植草さんは一体どういう人でどういう人生を歩んできたのか。生前親しくしていた担当編集者の方が丹念に書いています。
ファンキー老人としてブレイクする直前、中年期の植草さんは、太っていて、ポマードでなでつけたようなオールバック、三つ揃いのスーツを愛用という、アル・カポネみたいな容貌だったんだね!写真も載っていて確かに植草さんなんだけど、あの「おしゃれな仙人」みたいな雰囲気とは全く違った、脂ぎった中年おじさんみたいな感じで意外!このときは性格もかなり怒りっぽくて、すぐにちゃぶ台ひっくり返すようなキャラだったそう。それで人間関係も悪く、例えば、当時編集者だった常盤新平さんはかなり植草さんに嫌な目に合わされていたそう(というわけで仲は悪い)。
変化は植草さんの体調の変化で、大病をして入院したことで劇的に痩せて、あとは体が弱ったせいなのか性格も丸くなって、今知られているような、人当たりがよくて飄々とした人になったんだって。
仕事や経済的な面でも、実はこの老人期にブレイクするまでは不遇で、経済的にも苦労していたそう。もっとも植草さん自身が苦労するというよりも、奥様がということなんだけど。
奥さんからの植草さんの裏話も面白かった!私も植草さんのエッセイを読んで「散歩のたびになにか買い物をしないと気がすまない」とか「本やレコードをがさっと買ってくる」なんかのエピソードを読んで「買うのはいいけど、一体それらをどこに置いておくんだろうか…」と思っていたんだけど、やっぱり置き場所に苦労してたんだ!後年、やっと経済的に余裕が出てきて(今までと比較すると)大きな部屋に引っ越したのに、奥さんがちょっとスペースを空けておくと、あっという間に植草さんが本の束を置いちゃうんだって。ちなみに、奥さんは京都の老舗旅館の家の出で、戦争で被災して東京に出てきたところに、植草さんのお姉さんと知り合いになって植草さんを紹介されたとのこと。
本書では、植草さんの隠れたコンプレックスが考察されているのが白眉なんじゃないかな。勉強好きで博覧強記の植草さんだけど、当時の東大ヘ行くエリートコースに外れてしまったことで、商人の家の出身であることや、学歴コンプレックスを抱いてしまい、わりと後年まで引きずっていたんじゃないかと、身近で見ていた編集者の都野さんは書いています。現に、昔の映画評論の世界なんかでは、エリートコース以外の人を傍流とみなす雰囲気があったみたい。
植草さんの映画や小説の好み方がまた変わっていて、筋よりもイメージ。ストーリーとかは求めていなくて、場面場面の描き方やつなげ方に最大限の関心がある。だから大衆が好むわかりやすい作品は嫌いで、前衛的な作品が大好きだったんだって。こちらも、映画や小説の評論で、長らく不遇だった原因みたい。植草さんと仲の良かった淀川長治さん(植草さんの数少ない理解者)なんかは、ちゃんとこっちの筋のある作品の良さを熱弁できるものね。
赤ちゃんをお世話して変わったこと
こどもの世話をして変わったこと。
仕事や家事で困ったことや不愉快なことがあっても、「何か策があるはず」と前向きに対策を考えられるようになれたこと。元々、私はこういうときに対策を施すよりも、こうなった状況に対して恨んだり文句を言うところがあったので、それが抑えられてるのは嬉しい。
あとは、他の人や、自分のパラレル人生(私がもしこういう人生を歩んでいたら)みたいなものと、いたずらに比較しなくなったこと。これもいい。
この調子で頑張れ自分。
『大人の女は、こうして輝く。』久々に藤原美智子さんの近況を読む
90年代後半から0年代は雑誌の美容欄とか美容系の雑誌が好きで、そこによく登場するメイクアップアーティストの藤原美智子さんのライフスタイルを自然に追っているような感じでした。飼い犬のパピヨン・アデラちゃんとかね。藤原さんの日々の美容は、その時々でけっこう変化していたので、わりと読むたびにマイブームが変わるという感じだったかな。でも素敵なお手本みたいな感じで楽しく読んでました。
それが私自身雑誌を読まなくなってしまって、藤原さんの近況を追いかけるのもご無沙汰していたところ、こちらの本を見つけました。
現在の藤原さんは、ご結婚されて、新たなワンちゃんと暮らしているそうです。藤原さんが続けている美容も参考になりました。入浴前のドライブラッシングは私もやりたくなってしまってボディブラシ買っちゃった。「年をとるほど美容は結果が出るので楽しくなる」にも納得。
『台湾少女、洋裁に出会う――母とミシンの60年』
ミニシアターで素敵な小品を観終わった読後感。あとね、台南に行きたくなった!台南の路地裏とかね、ハヤシ百貨店(いまもあるらしい)とかね、見に行きたい。
本書の主な舞台は台南。主人公は著者のお母さんである施伝月さん。ずっと洋裁学校を運営してました。伝月さんは日本統治時代の台南に生まれ、少女時代に親戚の結婚式で見た白いウェディングドレスで洋服の世界に憧れ、家業の雑貨店で店番をさせられていた頃に見た、日本の婦人雑誌の洋裁のページ(雑誌の切れ端を貼りあわせて、商品を入れる紙袋にしていたそう)を扉に、見よう見まねの独学で洋裁の道に入りました。鬱々とした店番だけの日々に見るキラキラした雑誌から憧れが膨らみ、日本語という言葉の障壁に苦労しつつも独学で洋裁の勉強を始め、なんとか服が出来上がっていく興奮、読んでいるこちらもワクワクします。
当時の台湾は…って、たぶん日本もそうだったと思うけど「女が外に働きに行くなんて恥だ!とんでもない!」という時代。そんな中、なんとかお父さん(著者のおじいさん)を説得して、貧窮していたお父さんも「お金が入るんなら、まっいいか」とちゃっかり納得してw、伝月さんは当時の台南で一番オシャレで最先端の洋裁店に働きに行くことに成功します。(今や台湾といえば日本以上に女性の社会進出が進んでいるのにね)
洋服と洋裁が大好きで、ガッツがある伝月さんは洋品店でメキメキと頭角を現します。でも、若い男女がわいわい働いていた洋品店は恋愛沙汰も多くて、同僚のトラブルのとばっちりを食らって辞めることになるんだよね。でも既にその腕が評判になっていた伝月さんには、フリーになってからも仕立や、「洋裁を教えてほしい」という依頼がひっきりなしにやってくるんだよね。ここから後の洋裁学校の経営者となるきっかけが生まれてくるの。
伝月さんは、当時の台湾の価値観では全く「かわいくない女性」だそうでした。背がすごく高くて意志の強そうな顔立ちで。娘時代からよく「嫁の貰い手がないよ」なんて言われていたそうですが、でも写真で見る伝月さんは背が高いから洋服の着映えがして、顔立ちだってかっこいいし、すごく素敵です。
その後の伝月さんの人生、日本への留学、戦争をどう乗り越えたか、結婚出産育児、洋裁学校の設立と終焉…こちらはぜひ本書を読んでみてください!